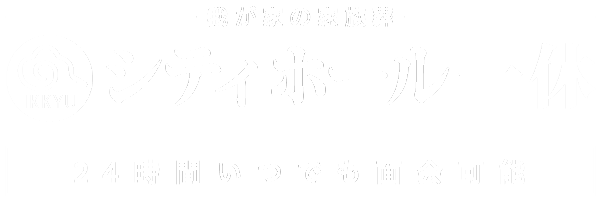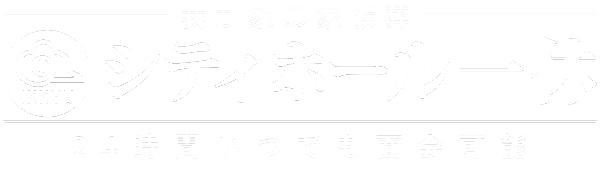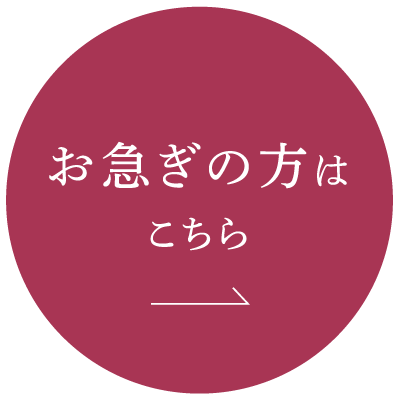葬儀を終えたあと、「これで一区切り」と思う方も多いかもしれません。
しかし、仏教のしきたりでは、葬儀後にも大切な行事がいくつか続きます。特に「四十九日(しじゅうくにち)法要」は大きな節目とされており、さまざまな準備が必要になります。
このシリーズでは、
【第一回】四十九日法要とその準備について
【第二回】本位牌・納骨・お墓の準備
【第三回】香典返しなど、気になるポイント
以上3回に分けて、わかりやすく解説します。
それでは、シリーズ1回目です。
=======================================================
四十九日法要ってなに? 日程と意味、そして準備の基本
大切な節目となる「四十九日法要」について説明します。
【今回の内容】
・四十九日法要の意味と目的
・法要はいつ行えばよい?日程の考え方
・僧侶や会場の手配はどうする?
・会場の選定ポイントは?

■四十九日法要とは
故人が亡くなられてから7日ごとに営まれる供養の行事を「忌日法要(きにちほうよう)」といいます。その中でも、亡くなった日から49日目にあたる「四十九日(しじゅうくにち)法要」は、特に大切な節目とされています。
この日には、親族や故人とご縁の深かった方々が集まり、故人が無事に成仏し、極楽浄土へ導かれることを願って法要を営みます。また、四十九日は、喪に服していたご遺族が少しずつ日常の生活へと戻り始めるきっかけとなる日でもあります。
法要の当日は、読経だけでなく、お墓への納骨や会食を通じて故人を偲ぶこともあります。さらに、新たに位牌を用意した場合は、魂を入れる儀式である「開眼法要(かいげんほうよう)」も一緒に行われます。
【四十九日法要に向けた準備と注意点】
■何を準備すればよいか?
葬儀が終わったら、できるだけ早めに「四十九日法要」の日時と会場を決めましょう。準備の際は、まず菩提寺(ぼだいじ)などのお寺に連絡をとり、僧侶の都合を確認します。また、法要のあとに行うお斎(おとき:食事会)に僧侶も参加してもらえるかどうかも確認しておくと安心です。
■日程を決める際の注意点
四十九日法要は、文字通り亡くなった日から49日目に行うのが基本です。ここで注意すべきは、「葬儀の日」ではなく、「亡くなった日」を1日目として数えるという点です。
ただし、必ずしも49日ぴったりに行わなければならないわけではありません。できるだけ多くの方に参列してもらえるように、日程は土日を選ぶことが一般的です。
■日取りを決めるうえでの注意は?
四十九日は、葬儀のように「友引」などの六曜(ろくよう)を気にする必要はありません。ただし、法要を「49日より後」にずらすのは避けたほうがよいとされています。これは、法要が遅れると、故人が迷って来世へ行けなくなると信じられているためです。
また、四十九日が「3ヶ月」にまたがることも避けるのが習わしです。これには「始終苦労(しじゅうくろう)が身につく」と言い伝えられており、縁起がよくないとされているからです。そのため、三ヶ月をまたがないよう、早めに日程を決めることをおすすめします。
■僧侶への依頼
四十九日法要を行うには、事前に僧侶へ読経の依頼をしておく必要があります。僧侶の予定が合わなければ、法要を予定どおりに行えなくなる可能性があるため、できるだけ早めに連絡・相談しておくと安心です。
先に僧侶の都合を確認してから日程を決めるという方法でも問題ありません。ただし、できるだけ四十九日に近い日程のほうが望ましいとされていますので、余裕を持って段取りを進めましょう。
■ 会場を選ぶポイント
法要を行う会場も早めの手配が必要です。
自宅で行う場合 == 気軽で費用も抑えられるが、準備の負担はやや大きめ
お寺やホール == 設備や対応が整っていて安心。早めの予約が必要
どちらを選ぶかは、人数や家庭の事情に合わせて検討しましょう。
【まとめ】
四十九日法要は、故人の成仏を願う大切な節目。
日程や会場、僧侶の手配は早めに進め、参列者への案内や会食の有無も決めておきましょう。
大切なのは、故人を想う気持ちと、無理のない準備です
次回(第2回)は、本位牌・納骨・お墓の準備についてわかりやすく解説します。