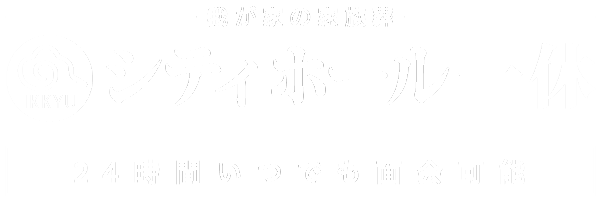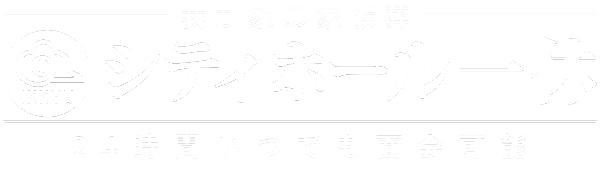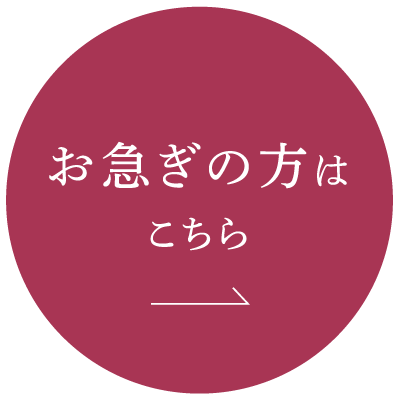葬儀の後、四十九日法要と一緒に行われることが多いのが、納骨(のうこつ)と本位牌(ほんいはい)の準備です。この回では、納骨や位牌の流れ、注意点をわかりやすくご紹介します。
【今回の内容】
・納骨のタイミングと納骨式の流れ
・お墓の準備に必要な手続きとは
・戒名の彫刻や石材店への依頼方法
・本位牌の準備手順と注意点
・位牌に記載する情報やサイズの選び方
◼️お墓の準備について
納骨を行う時期に明確な決まりはありませんが、仏教の慣習では「四十九日法要」にあわせて納骨を行うのが一般的です。そのため、四十九日と納骨を同じ日に行う場合は、あらかじめお墓の準備を済ませておく必要があります。
納骨を行う際には「納骨式」という儀式も行われるため、菩提寺の僧侶と相談のうえ、日程を決めておきましょう。日程が決まったら、次の2点についても事前に連絡しておきます。
•墓地の管理事務所 : 当日の立ち会いや鍵の手配などをお願いするため
•石材店 : 墓石または墓誌に故人の「戒名」を彫刻してもらうため
なお、地域によっては、葬儀の際に初七日法要と四十九日法要をまとめて行い、その日に納骨まで済ませるケースもあります。しかし、お墓の準備が整っていないと納骨できないため、四十九日までに間をあけて行うのが一般的です。
お墓の購入には高額な費用がかかることも多いため、前もって計画的に準備しておくことが大切です。もしお墓を準備できない場合は、「永代供養」や「海洋散骨」など、別の供養方法を選ぶこともできます。

◼️本位牌の準備について
四十九日法要と納骨を同じ日に行う場合は、本位牌(ほんいはい)も事前に用意しておく必要があります。本位牌とは、仏壇に安置する正式な位牌のことで、仏具店で購入し、「戒名」「没年月日」などを彫ってもらいます。
通夜の際に使用した白木の位牌(仮の位牌)は、四十九日の納骨時に菩提寺へ納め、法要後は本位牌を仏壇に安置します。
本位牌の準備には通常、1~2週間程度かかるため、できるだけ早めに依頼するのがおすすめです。以下は、準備の手順です。
〈本位牌をつくるまでの流れ〉
1.必要な情報を整理する
以下の内容を正確に控えます。
- 戒名(仏名)
- 俗名(生前のお名前)
- 命日
- 享年(年齢)
2.位牌の大きさを確認する(仏壇がある場合)
既に仏壇に他の位牌がある場合は、その大きさに合わせると見た目が整います。
3.仏具店に依頼する
位牌づくりに対応している仏具店を探し、控えた情報を伝えて依頼します。
4.完成したら受け取り
仏壇に安置する位牌が完成したら受け取りに行き、四十九日の法要を目安に仏壇へ安置します。
【まとめ】お墓と位牌の準備は「時間に余裕を持って」
納骨や位牌の準備には、思ったよりも時間がかかります。
お墓の契約や石材店の手配、本位牌の発注や仕上がり時間など、早め早めに動くことが安心につながります。
次回は、香典返しや会食、参列者への案内など、実務的な準備についてご紹介します。