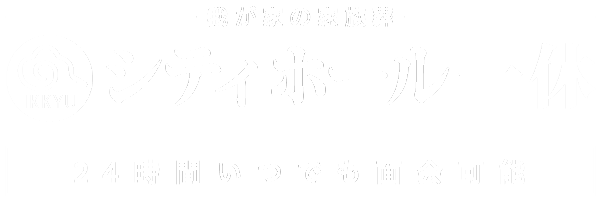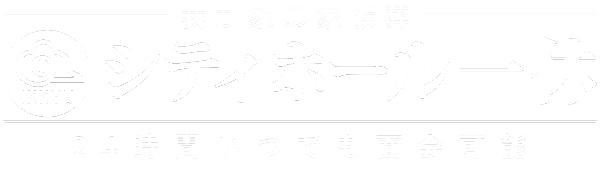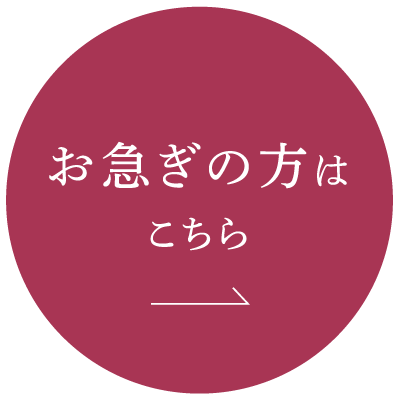今回は、香典返しや会食(お斎)など、四十九日法要の実務について説明します。
【今回の内容】
・香典返しの時期・金額・品物の選び方
・案内状の書き方とマナー
・会食(お斎)の手配と料理形式
◼️香典返しの準備
香典とは、本来「お返しを必要としないお悔やみの気持ち」として贈られるものですが、日本の慣習として、香典をいただいた方に品物をお返しする「香典返し」を行うことが一般的になっています。
最近では、葬儀や法要の当日に「会葬御礼」と「香典返し」の品を一緒にお渡しし、参列者に持ち帰ってもらう形式も増えています。
香典返しの金額の目安は、いただいた香典の「半額から3分の1程度」とされています。たとえば、参列者が5,000円の香典を包んだ場合、2,000~3,000円ほどの品を選ぶのが一般的です。
ただし、香典は一家でひとつお包みいただくことが多いため、参列者の人数と香典返しの数が一致するとは限りません。数の見積もりには余裕を持たせましょう。
香典返しをお渡しする時期については、仏式では「三十五日忌」や「四十九日忌」といった忌明けの頃が一般的です。

◼️法要参列者(招待者)の範囲を決める
参列者の範囲に特にこだわりがない場合は、親族全員を招待するのが無難です。もし故人の希望が「家族だけで行ってほしい」など明確であれば、それに従うのがよいでしょう。
故人の意向が分からない場合は、後々の人間関係に配慮し、親族一同を招くことをおすすめします。
また、参列者の人数によって法要の場所を決める必要があります。自宅であれば予約の必要はありませんが、お寺やセレモニーホールなどを利用する場合は、早めの予約が必要です。参列者の規模をある程度想定し、場所だけでも先に押さえておくと安心です。
◼️案内状の準備と発送
四十九日法要の日時と場所が決まったら、参列をお願いしたい方へ案内状を送付します。
案内状には、仏事のマナーとして「縦書きで書くこと」「句読点を使わないこと」が一般的です。句読点の代わりには、行間や空白を使って読みやすさを工夫します。
案内状に含めるべき内容は、以下の通りです
- 季節の時候の挨拶
- 四十九日法要のご案内
- 参列をお願いする旨
- 法要の日時・場所
- 会食の有無
- 返信方法・返信期限
- 施主(主催者)の氏名・連絡先
なお、少人数や身内のみで行う場合は、電話での連絡でも構いません。その際は、日時・場所・持ち物・返信の有無など、伝え漏れのないように注意しましょう。

◼️食事(会食)の手配について
四十九日法要のあとの会食を行うかどうかは、家庭や地域の習慣によって異なります。必ず行わなければならないものではありませんが、一般的には「お斎(おとき)」と呼ばれる会食が行われます。
お斎は、法要に参列してくださった方々と一緒に故人を偲ぶための時間で、厳密な決まりごとはありません。故人が生前に好んでいた料理を用意するなど、故人らしさを感じられる内容にすることもあります。
なお、大皿料理や立食形式は避けたほうが無難です。どうしても場が賑やかになりがちで、法要の場としてふさわしくない雰囲気になってしまうことがあるためです。参列者一人ひとりにお膳形式で料理を提供するのが一般的です。
食事を注文する際には、「四十九日法要後の会食用」であることを事前に伝えておくと、料理内容や配慮も含めてスムーズに手配できます。
また、法要を自宅で行う場合は、そのまま自宅で会食を振る舞うケースも多く見られます。とはいえ、ご遺族のご負担が大きい場合は、近隣の料理店や会席料理店を利用しても問題ありません。
人数や当日の手伝いの有無などを踏まえ、自宅で行うか外で行うかを早めに検討しておくと安心です。
【まとめ】
四十九日は心と形の区切りの日
香典返しや食事、案内状など、細かな準備が多い四十九日法要。
それぞれにマナーや段取りはありますが、大切なのは「感謝の気持ち」と「故人への思い」です。
準備に不安があるときは、葬儀社や仏具店、僧侶など、専門の方に相談すると安心です。